「7つの習慣」と「嫌われる勇気」という本が 未だに世界各国で、注目を浴びる。判り易い解説をYoutubeで見てみよう。中身をしっかり反芻しよう。
時折、原点に立ち返り、振り返ることは大切だ。
生きる姿勢を検証できるし、視点も異なるので勉強になる。賢者のお話は示唆に富む。あ~しあわせ。
The book “Seven Habits” and “Hate Courage” are still attracting attention around the world. Let’s see the easy-to-understand commentary on Youtube. Let’s think the contents well.
Occasionally it is important to look back to the starting point.
You can study your attitude to live and learn from different perspectives. The wise man’s story is suggestive.
we are so happy to know.
_________________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ①
娘たちは、健気で可憐だ。微笑ましく眺めてしまう。
_______________
___________________________
___________________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ②
家人が 良く土を手入れして 栄養が行き渡っている。思わず、目を細めて話しかけてしまう。
_______________
111①.【7つの習慣まとめ】10分で分かりやすく解説!(自己啓発)108,257 回視聴 2019/05/01  ライフハックアニメーション【心理学・健康・仕事術の話】 チャンネル登録者数 8.29万人
ライフハックアニメーション【心理学・健康・仕事術の話】 チャンネル登録者数 8.29万人
【💡この動画のポイント】
・7つの習慣の全体的な構造が分かる!
・7つの習慣それぞれについて要点が掴める!
・7つの習慣の目指す所が分かる!
この動画では、全世界で3000万部、国内では180万部を超え、 今もなお読み続けられる人生哲学の定番「7つの習慣」について、 要点を分かりやすくまとめて約12分で紹介しています。 7つの習慣の著者は、嫌われる勇気でもお馴染みのアドラー心理学からも強い影響を受けているとされており、 アドラー心理学についても一緒に学ぶとより効果的です。
_________________________
_________________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ③
土の表面を眺めていると娘たちが喜んでいるのが良く判り嬉しい。
_______________

____________________________
____________________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ④
白い丸い粒は 栄養だが 名前を忘れた。
________________
111③. ロングセラー本「7つの習慣」を7分で解説!
_____________________
____________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ⑤
____________
______________
_____________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ⑥
_____________
222①. 嫌われる勇気|承認欲求は生ゴミでした。 82,415 回視聴 2020/01/07 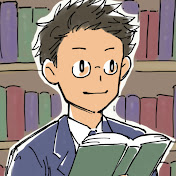 サラタメさん【サラリーマンYouTuber】
サラタメさん【サラリーマンYouTuber】
チャンネル登録者数 18.8万人
______________________
_______________
ウィキペディアから抜粋:
アドラー心理学(アドラーしんりがく)、個人心理学(こじんしんりがく、英: individual psychology)とは、アルフレッド・アドラー(Alfred Adler)が創始し、後継者たちが発展させてきた心理学の体系である。個人心理学が正式な呼び方であるが、日本ではあまり使われていない。
日本におけるアドラー心理学の第一人者である岸見一郎氏によれば、もともとはジークムント・フロイトとともに研究していたが、その学説はフロイトの理論とは大きく異なり、たとえば苦しみの原因をトラウマに求めないことなどがあげられる。
__________

1月の誕生花 水仙
__________
アドラー自身は自分の心理学について、個人心理学(ドイツ語: Individualpsychologie)と呼んでいた。それは、個人とは分割できない存在である、と彼が考えていたことによる。
アドラーが自分の心理学について個人心理学と呼んだように、アドラー心理学では、個人をそれ以上分割できない存在であると考えることから、人間の生を、個人という全体が個人の必要な機能等を使って目的に向かって行動している、というふうに考えている。
より具体的には、人間は相対的にマイナスの状態(劣等感を覚える位置)から、相対的にプラスの状態(優越感を覚える位置)を目指して行動している、と考えている。
_____________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ⑦
______________________
222②.Alfred Adler: 1. Life and Times
___________
________________________
アドラー心理学の理論的な枠組みは、次の5つを基本前提として受け入れていることによって成立している。
5つの基本前提(5Basic Assumptions)
- 個人の主体性(Creativity)
- アドラー心理学では、個人をそれ以上分割できない存在であると考えることから、全体としての個人が、心身を使って、目的に向かって、行動している、ととらえる。アドラー心理学では、個人の創造力、創造性を評価していて、それが個人の変化、変容を可能にする根拠となっているので、主体性というより創造性の方が適切である。
- 目的論(Teleology)
- 全体としての個人は、生物学的には、個体保存と種族保存、社会学的には、所属、心理学的には、その人らしい所属、という目標のために行動する。
- 全体論(Holism)
- アドラー心理学では、個人を、例えば、心と身体のような諸要素の集合としてではなく、それ以上分割できない個人としてとらえる。したがって、アドラー心理学では、心と身体、意識と無意識、感情と思考などの間に矛盾や葛藤、対立を認めない。それらは、ちょうど自動車のアクセルとブレーキのようなものであって、アクセルとブレーキは互いに矛盾し合っているのではなく、自動車を安全に走行させるという目的のために協力しているのと同じように、個人という全体が、心と身体、意識と無意識、感情と思考などを使って、目的に向かっているのである。
___________

___________
- 社会統合論(Social Embeddedness)
- 人間は社会的動物であることから、人間の行動は、すべて対人関係に影響を及ぼす。
- アドラー心理学では、人間が抱える問題について、全体論から人間の内部に矛盾や葛藤、対立を認めないことから、人間が抱える問題は、すべて対人関係上の問題であると考える。
- 人間は人間社会において生存しているものであって、その意味で社会に組み込まれた社会的存在なのである。社会的存在であるので、対人関係から葛藤や苦悩に立ち向かうことになるが、個人の中では分裂はしていなくて一体性のある人格として行動している。
- すべての行動には対人関係上の目的が存在している。社会に統合するというよりも、最初から社会的存在なのである。
___________
___________
- 仮想論(Fictionalism)
- アドラー心理学では、全体としての個人は、相対的マイナスから相対的プラスに向かって行動する、と考える。
- しかしながら、それは、あたかも相対的マイナスから相対的プラスに向かって行動しているかのようである、ということであって、
- 実際に、相対的にマイナスの状態が存在するとか、相対的にプラスの状態が存在するとかいうことを言っているのではない。
- 人間は、自分があたかも相対的マイナスの状態にあるように感じているので、それを補償するために、あたかも相対的プラスの状態を目指しているかのように行動するのである。
- これは哲学における認知論の問題である。
- ただし、「認知」という用語の使い方については、基礎心理学(臨床治療を直接の目的としない研究)の20世紀後半以降の主流派であるところの認知心理学における「認知」とは大きく異なることに注意が必要である。
_________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ⑧
_________________
222③.嫌われる勇気の「課題の分離」をもっと詳しく!分かりやすく!【アドラー心理学】60,650 回視聴 2019/07/11  ライフハックアニメーション【心理学・健康・仕事術の話】チャンネル登録者数 8.29万人
ライフハックアニメーション【心理学・健康・仕事術の話】チャンネル登録者数 8.29万人


______________________
______________________

2020年1月12日(日)我が家の玄関 ⑧
_____________
技法
アドラー心理学の治療、または、カウンセリングは、上記の理論に基づいて、後述する来談者の共同体感覚を育成することが目的である。
アドラー心理学においては、治療、または、カウンセリングの技法は、上記の理論に基づいて、来談者の共同体感覚の育成を目的として、適宜適切な技法が選択されるので、治療、または、カウンセリングの技法その部分だけを取り出すと、認知主義、認知行動主義、短期療法などの諸派の治療技法と同様に見られることがある。
しかしながら、後に、認知主義、認知行動主義、短期療法などに分類される様々な治療技法に関して、既にアドラー自身が用いていた技法も多い。
アドラー心理学に基づいた治療、または、カウンセリングでは、アドラー心理学の理論に基づいて、来談者の共同体感覚を育成する目的で、様々な技法が用いられる。
そのような治療中、または、カウンセリング中に、治療者、または、カウンセラーが、常に意識しているのは、来談者のライフスタイルについてである。
ライフスタイル分析(Lifestyle Analysis)
ライフスタイルは、アドラー心理学の重要な鍵概念のひとつである。
ライフスタイルとは、その人が、自分自身をどのような相対的マイナスの状態にあると考えていて、それを補償するために、どのようなプラスの状態を目指していて、それを達成するためにどのような手段を用いているか、というその人の人生の運動全体のことである。
これは、アドラー心理学の人間理解の根本であるから、来談者のライフスタイルを分析するライフスタイル分析は、アドラー心理学独自の技法である。ライフスタイル分析は、治療、または、カウンセリングの必要に応じて行われる。
3つのライフタスク(Life Tasks)
アドラー心理学では、人間の問題は、すべて対人関係上の問題であると考える。したがって、アドラー心理学の治療、または、カウンセリングにおいては、
来談者が抱えている問題は、対人関係上の問題であり、来談者が自らの資源(Resource)や使える力(Personal Strength)をうまく工夫すれば解決できるライフタスクであると考えている。アドラー心理学では、ライフタスクについて、来談者にとっての親疎の関係から次の3つに区別している。
- 仕事のタスク(Work Task)
- 永続しない人間関係。
- 交友のタスク(Friendship Task)
- 永続するが、運命をともにしない人間関係。
- 愛のタスク(Love or Family Task)
- 永続し、運命をともにする人間関係。もともとアドラーが述べていたのは、人類の存続に関する課題でもあり、男女の愛情関係が中心であったが、その後の進展で家族の問題も含まれるようになっている。
人間の問題について、このように恣意的に3つに分類することは、臨床上極めて有効で、
アドラー心理学独自のことである。
もう長い間、わたしは次のように確信している。それは、人生のすべての問題は、3つの主要な課題に分類することが出来る。すなわち、交友の課題、仕事の課題、愛の課題である。
________________

2020年1月12日(日)我が家の庭 ⑨
________________
222④.Adler and Trauma – Anthea Millar

______________________
______________________



